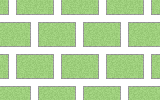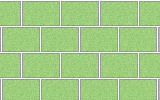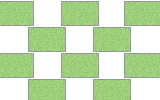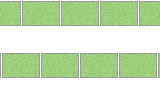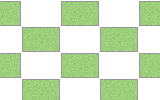これまでの準備が整ったらついに芝生の造成です。
芝生の造成方法には下の3つの方法があります。
その中でもシバウラは、短期間で造成が可能な「芝張り」をお勧めいたします。
播種
芝草の種を整地した床土に蒔く方法です。
施工費・材料費が低く抑えられますが、施工できる期間が限られ、また芝生が使用できるまでの時間が掛かるため大雨で種が流されてしまうなど、気象条件の影響も受けやすい造成方法です。
芝張り
平板状の芝生(ソッド)を整地した床土に張り付ける方法で、短期間で造成可能なので最も一般的に用いられる造成方法です。
ただし、張った芝生と床土の間に不透水層ができる可能性が高く、早めの更新作業(エアレーションなど)が必要となる場合があります。
芝張りの時期は、春が望ましいとされています。それは芝張り後に芝が生長し続ける時間を最も長く取れるからです。
しかし、十分な管理を行えば、難易度は増しますが年間通していつでも行うことができます。
一般的に芝生は、1m²を9等分した9枚1束のソッドで販売されており、これを整地した土壌に並べます。
シバウラでは「目地張り」をお勧めいたします。
それは「目地張り」は芝生の完成までに時間がかかり、雑草が入る可能性が高い張り方ではありますが、目地を埋めようと芝生の生育が活発になるなど、芝の生育と造成のための初期コストを抑えられるからです。
芝を張った後は、ローラーを用いて芝草の根がしっかりと土壌に密着するように押さえつけましょう。(ローラーが無い場合は足で踏みましょう)
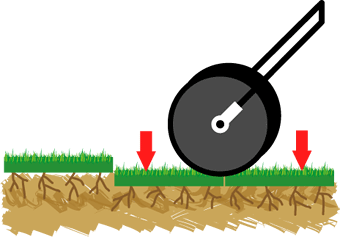
その後、十分な量の水を撒き、完全に仕上がるまでの2~3ヶ月間は養生を行います。(造成時のみ)
養生の間は、基本的に芝生への立ち入りは禁止とし、しっかりと根が伸びるまでは乾燥させないように気を配りましょう。養生に要する期間は芝張りの時期によって異なりますが、これから寒くなる秋口に実施した場合には、最大翌年の春まで養生が必要となります。
Warning: include(/home/shibaura/ihi-shibaura.com/public_html/schoolyard/banner_mailmagazine.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/tanakara2017/ihi-shibaura.com/public_html/schoolyard/process/process_side.inc on line 2
Warning: include(): Failed opening '/home/shibaura/ihi-shibaura.com/public_html/schoolyard/banner_mailmagazine.inc' for inclusion (include_path='.:/opt/php-7.4.33-2/data/pear') in /home/tanakara2017/ihi-shibaura.com/public_html/schoolyard/process/process_side.inc on line 2
Warning: include(/home/shibaura/ihi-shibaura.com/public_html/schoolyard/banner_green.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/tanakara2017/ihi-shibaura.com/public_html/schoolyard/process/process_side.inc on line 3
Warning: include(): Failed opening '/home/shibaura/ihi-shibaura.com/public_html/schoolyard/banner_green.inc' for inclusion (include_path='.:/opt/php-7.4.33-2/data/pear') in /home/tanakara2017/ihi-shibaura.com/public_html/schoolyard/process/process_side.inc on line 3